空の街(サンプル)
北欧神話の小説です。
書下ろし1作を収録しています。
・書下ろし
「空の街」(ロキ、トール、他)
B6サイズ:60P:400円
2019/09/08「第七回文学フリマ大阪」で発行
2024/05/05「SUPER COMIC CITY 31 -day2-」で再版
◆表紙と本文のイメージ(再版は少し異なっています)

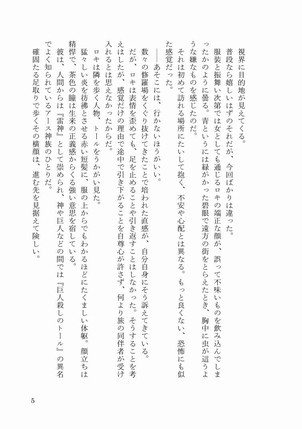
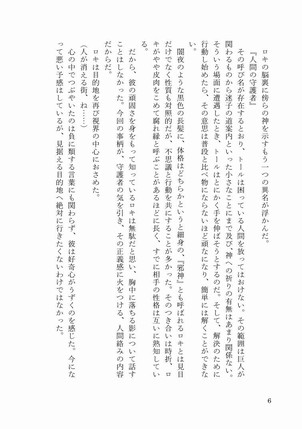
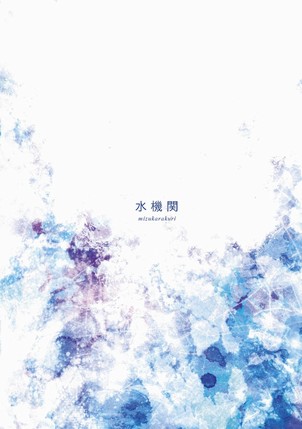
*もう少し種類と大きめに見る→pixiv
◆本文サンプル
人が消える、という街の謎を解明しようと街を訪れたロキとトールの話
※本では縦書きになります
視界に目的地が見えてくる。
普段なら嬉しいはずのそれだが、今回ばかりは違った。
服装と振舞い次第では女としても通じるロキの端正な顔が、誤って不味いものを飲み込んでしまったかのように曇る。青というには緑がかった碧眼で遠方の街をとらえたとき、胸中に虫が這うような嫌なものを感じたのだ。
それは初めて訪れる場所にたいして抱く、不安や心配とは異なる。もっと良くない、恐怖にも似た感覚だった。
――あそこには、行かないほうがいい。
数々の修羅場をくぐり抜けてきたことで培われた直感が、自分自身にそう訴えてきている。
だが、ロキは表情を歪めても、足を止めることや引き返すことはしなかった。そうすることを考えはしたが、感覚だけの理由で途中で引き下がることを自尊心が許さず、何より旅の同伴者が受け入れるとは思えなかったからだ。
ロキは隣を歩く人物、トールをうかがい見た。
猛々しい炎を彷彿とさせる赤い短髪に、服の上からでもわかるほどにたくましい体躯。顔立ちは精悍で、茶色の瞳は生来の正義感からくる強い意思を宿している。
彼は、人間からは『雷神』として崇められ、神や巨人などの間では『巨人殺しのトール』の異名でよく知られているアース神族のひとりだ。
確固たる足取りで歩くその横顔は、進む先を見据えて険しい。
ロキの脳裏に傍らの神を示すもう一つの異名が浮かんだ。
『人間の守護者』
その呼び名が存在するとおり、トールは困っている人間を放ってはおけない。その範囲は巨人が関わるものから迷子の道案内といった小さなことにまで及び、神への祈りの有無はあまり関係ない。そういう場面に遭遇したとき、トールはとにかく手を伸ばそうとするのだ。そして、解決のために行動し始めたら、その意思は普段と比べ物にならないほど頑なになり、簡単には解くことができない。
闇夜のような黒色の長髪に、体格はどちらかというと細身の、『邪神』とも呼ばれるロキとは見目だけでなく性質も対照的だが、不思議と行動を共にすることが多かった。そのつき合いは時折、ロキがやや皮肉をこめて腐れ縁と呼ぶことがあるほどに長く、すでに相手の性格は互いに熟知している。
だから、彼の頑固さを身をもって知っているロキは無駄だと思い、胸中に落ちる影について話すことはしなかった。今回の事柄が、守護者の気を引き、その正義感に火をつける、人間絡みの内容だからだ。
ロキは目的地を再び視界の中心におさめた。
(人が消える街、ね……)
心の中でつぶやいたのは負に類する言葉にも関わらず、彼は好奇心がうずくのを感じた。今になって悪い予感はしているが、見据える目的地へ絶対に行きたくないわけではなかった。
昨日、耳にしたあの街に関する話への興味が、今は多少そがれたとはいえ、まだ残っているからだ。
事の発端となる奇妙な話を聞いたのは、目的地から少し離れたところに位置する街でだった。
(はー、やっとまともに休める)
宿の一室。ロキは凸凹とした固い地面ではなく、平らで柔らかな布の敷かれた寝台に三日ぶりに身を横たえられる幸せをひしひしと噛み締めていた。
(……俺も街中を見てまわりたいけど……先に一眠りするか)
木造の天井を視界に入れたまま、そんなことを考える。
旅の同行者であるトールは野営の疲れなど一切ない様子で、まだ日が高いからちょっと街の中を見てくると言って宿から出ていった。本当に肉体ばかり頑丈なやつである。
ふあぁとロキが欠伸をする。瞼がゆるゆると降りていき、一分と経たずに虚ろな碧眼を覆い隠した。
窓の外から室内に、陽光がやわらかく射し込み、物音がおぼろげに響いてくる。
ふたりが宿泊する宿は街の中心部から離れた位置にあるためか、わりと規模の大きい街にも関わらず、昼間でも実にのどかだ。
微睡んでいたロキの意識が、ゆっくりと静かで深い暗闇へと落ちていく。
そして、心身が幸せな静けさに包まれる、寸前だった。
「――ロキ!」
ばたんっと大きな音を立てて勢いよく部屋の扉が開いた。
「ロキ! 大変だ!」
「っ……、なんだよ、トール」
空気を震わす大声と床をみしみしと鳴らす足音が、ロキの意識を強制的に明るさの中に引き上げた。
心地よい空間を壊され、半身を起こしたロキが顔をしかめて、近づいてきたトールを睨みつけるように見る。しかし、視線が合っても相手の茶色の眼は怯むことなく、その表情は真剣なままだ。
「人が消えるらしい!」
「は?」
「だから、街から人が消えるらしいんだ!」
「……この街から人が消える?」
「違う!」
「……おい、トール」
放たれた妙に曖昧な言葉を自分なりに噛み砕いて返した科白を即座に否定されて、ロキは眉間の皺を濃くした。
「少し落ち着け。それから話せ」
やや鋭く低くなった語調と変化した表情を受けてトールが軽く息を呑む。察したのか、三呼吸挟んでから口を開き直した。
「さっき、この街の人間から話を聞いたんだ。ここから北にある街で、人が消えていく現象が起きているって。ロキ、すぐに調べに行こう」
眉尻を引き上げて言うトールに、ロキはしかめ面から鋭さを引いて、応える代わりに欠伸を一つした。
「ロキ!」
「トール、人が消えるって、単に夜逃げとかそういうのじゃないのか?」
「そうじゃない。ほら、この手紙」
トールが懐から折りたたまれた一枚の紙を取り出してロキに差し出す。
ロキは訝しく思いながら、受け取った紙を開いて中を見た。
親愛なるアザへ。
本当なら、君にこのような手紙を送りたくはなかったが、もはや、わたしの力ではどうすることもできない。
ひと月ほど前から、街で奇妙なことが起きている。突然、街民が行方不明になるんだ。いつも通りに会った人が、翌日になると忽然と姿を消してしまう出来事が多発している。調べたが、人攫いや夜逃げの類ではない。
街への悪評を防ぐために街の者だけで解決しようとしたが、行方不明の人の手がかりも原因も全くつかめなかった。
この街の長となってから十年になるが、こんなことは初めてだ。
各地を旅したことのある博識な君なら、何か似たような出来事を知っているのではないかと思い、この手紙を送った次第だ。
頼む。原因を究明し、消えた者を捜し出すために力を貸してほしい。
ところどころ乱れのある文字で綴られた手紙から目を離し、ロキはトールに視線を戻した。
「それで?」
「え」
「この手紙のあとはどうなったんだ?」
冷静な口調でロキが問うと、トールは顔に暗い色を滲ませてどこか絞り出すように答えた。
「その手紙を受け取った人間はその街に行って、未だに戻っていないそうだ。連絡もない。手紙は、奥さんから預かったんだ。なぁ、ロキ、調べに行こう」
茶色の瞳には憂いの中に燃え立つ炎のような感情が見え隠れしている。
まっすぐな相手の視線を無言で十秒ほど受け止めてロキは、ふぅとため息を吐いて寝台に寝転がった。
「ロキ! 大変なことが」
「トール。落ち着け。誰も調べに行かないとは言ってないだろ」
「! じゃあ、」
「だが、行くのは今すぐにじゃない。明日だ。早く行きたい気持ちはわかるが、俺達はここまでの旅路で疲れている。そんな状態で行って、何かあったときに最善な対応ができるか? 今日は明日に備えて休むんだ」
「……わかった」
ロキの言葉にしぶしぶという調子ながらもトールはうなずいた。まだ覇気の抜けきらない様子でもう一台の寝台のほうへ行き、そばに置いてある自分の荷物をごそごそとし始める。
真剣な面持ちで旅支度を確認するトールを横目で見てから、ロキは手にしている手紙にもう一度目をやった。
(人が消える、か)
それは嘘か誠か。
どちらにしろ、退屈はしなさそうだ。
そんなことをロキはぼんやりと思った。
一歩進むごとに目的地が、遠くに広がる山や空などの他の景色とは切り離され、一つの個としてのたしかな存在感をもっていく。同時に、心身に覚える不穏な感覚も強さを増していく。
ロキは重くなる気分を少しでもやわらげようと、街に据えていた視線を外して周りを見た。緑を抱く木々に白や黄色の草花、薄い雲の漂う青い空、雪をかぶった灰色の山脈。風が吹くと葉が乾いた音を立てて、ときどき鳥が小さな鳴き声を上げて飛んでいく。
(……ん?)
不意に引っかかるものを感じてロキは足を止めた。今度はじっくりと四方に視線を巡らせる。
「ロキ? どうしたんだ?」
三歩ほど先で、ロキの異変に気づいたトールが立ち止まって振り返った。
ロキは訝るトールに顔を向けながら口を開く。
「変だ。街を出てからここまで誰も見かけてない」
「そうだったか……? 偶然じゃないのか?」
「まだ昼前だぞ。これだけ整備されている道なら、人の往来が多いはずだろ。なのに、ひとりも会わないなんておかしい」
「………」
トールが黙って同じように周囲を見回す。一周したところでその顔が渋面を作った。
今ふたりは、林の中に作られた一本道の途中にいる。邪魔な木を切り、極力平らにならされた地面は踏み固められていて、この場所の必要性を物語っている。
しかし、人の気配は全くない。きた先も行く先も、整えられた地面がただ続いているだけだ。あるべきものの喪失を意識すると、のんびりとした静けさが物寂しさを越えて不気味に感じられてくる。
これは、向かう街に起きているという不可思議な現象と関連があるのだろうか。
風が止まり、小さな葉擦れの音が消え、鳥の鳴き声も響かない。沈黙がふたりの間に重く鎮座する。
「……ロキ」
ややあって、トールが名前を呼んでロキをまっすぐ見た。
「様子がおかしいのなら、なおさら、街に行く必要がある」
碧眼をとらえる茶色の双眸は揺らがず、これまでと変わらない強い光が宿っている。
「わかってるよ」
こんなことで彼の意思がくつがえらないことは、だいぶ前からわかっていたことだ。
ロキはトールの隣に並んだ。
「油断するなよ」
「ああ」
ふたりは一度互いの意思を確認するように顔を見合わせると、道の先の目的地へ向け、歩みを再開した。
青い空の下、薄い灰色の石で作られた三角屋根の建物が建ち並んでいる。地面は正方形に切り出された石畳が敷かれ、石の無機質な雰囲気を補うように道の端や建物に色とりどりの花が飾られている。奥に、街に使われている石と似た色をした大きな岩山がそびえているのが建物の間から垣間見える。
ロキとトールが何事もなくたどり着いた街は、昨日宿泊した街とほぼ同じ規模で、整然とした街並みから石の資源が豊富で潤っているのだと知れた。
綺麗な街だ。ずっと抱き続けている不快な感覚のせいで荒廃した街を想像していたロキだったが、実際の街を眼前にするとそう感じた。外から一見した印象では、こんな場所で人が消えるという奇妙な現象が起きているとは到底思えない。
だが、街中に入って三十分ほどで、ロキとトールは異常をはっきりと認識した。
「おかしいな」
「誰もいない」
人間を誰ひとりとして見かけない。
それどころか、猫や犬など人間以外の生物の姿もない。時折立ち止まって耳を澄ませてみるが、生物が立てるような物音は一切聞こえてこず、声を上げてみても応答はなかった。
街に争いなどがあった形跡はなく、今まさに誰か出てきてもおかしくないほどに生活感の残る状態だ。
静まり返った街の様子は、ここにくるまでの道中で覚えた違和感と酷似している。
「……ここもいないか」
ロキは五軒目になる建物の扉を叩き耳を当てて内部の気配や音を探ってみたが、結果はこれまでと変わらずで収穫は何もなかった。
応答のない扉を見つめ、ふと、頭に浮かんできた提案を口にする。
「無理矢理中に入ってみるか?」
「ロキ!」
「冗談だよ」
破壊活動を心配するトールにロキは肩をすくめて建物から離れた。
あらためて四方を見回すが、やはり自分達以外の生物は影も形もない。
(住民が全員もう消えたのか? だとしたら、まずいな)
現象についての話を聞くことができない。これは解決に時間がかかりそうだ。少しでも何か手がかりを探さなければ。
ロキは別の建物のほうに足を進めた。
「……?」
しかし、扉の前にたどり着く前に立ち止まる。振り返って視線をゆっくりと周囲に巡らせる。変わらない石造りの景色、その中にいるのは旅の共だけだ。
「ロキ?」
「トール、今何か聞こえなかったか?」
「いや……」
――ナァ
疑問を帯びた控えめな声に異種の音色が重なった。
それは葉擦れや連れの声とは違う、この街では初めての音だ。一度目は微かに聞こえただけで空耳かとも思ったが、二度目のそれで確信を得た。
ロキは視線を素早く辺りに走らせる。
頭上に目をやったとき、建物の上に眩しい陽光を背にした黒い何かを見つけた。逆光のために輪郭をはっきりととらえることはできないが、しなやかな曲線は人工物ではなく生き物のように思えた。
(あれが、音の発信源か……?)
だが、ゆっくりとその正体を見定めている余裕はなかった。
注視する黒い何かが、屋根の上で大きく動いたのだ。
「!」
ちょうどそれが自分のほうへ降ってくるのに気づき、ロキは急いで後ろに飛び退いた。
黒い何かはロキが立っていた場所の近くに軽やかに着地した。
飛び降りてきたものの正体にロキは顔をしかめ、そばに駆け寄ってきたトールがやや驚いた様子でつぶやく。
「猫……?」
艶やかな漆黒の毛に覆われた身体に、まっすぐふたりを見据えるのは金色の眼。
トールの言葉のとおり、現れたのは一匹の黒猫だった。
茫然としているふたりが行動を起こす前に、黒猫はまた一つ鳴くと、身を翻して駆け出した。
――追いかけなければ。
「ちっ、待て!」
「お、おい、ロキ!」
ロキは舌を打ち、黒猫のあとを追う。一足遅れてトールも続く。
黒猫をとっさに追いかけることにしたのは、具体的な理由があったからではない。ただ、前を走る黒い獣がここで出会った初めての生き物だったからだ。手がかりが何もない現状で、他にどうすればいいのかも定まってない。役に立つのかわからないものでも、ひとつまみの可能性があるのなら、見逃すわけにはいかなかった。
黒猫は軽快な足取りで、石畳の上を飛ぶように駆けて行く。振り切られてしまうような速さではないが、なかなか手の届く範囲までには追いつかない。
(くそ……)
焦れったくなる、つかず離れずの距離に、ロキが魔術を使うことを考えたとき、黒猫が大通りから右の路地に入っていった。
ふたりも躊躇いなく同じ所で曲がる。
だが、ほどなくして足を止めざるを得なくなった。
「どこに行った?」
追っていた猫の姿が、前方に続く道のどこにも見当たらない。
ロキとトールは慌てて周囲を見回した。
そこは今まで通ってきたところよりも幅が狭い道だ。だが、それ以外は特別変わったところはない。道の両側には身長よりも高い石造りの建物が並び、その窓や扉は外部の何者も拒絶するように閉じられている。壁面に猫が通り抜けできるような穴はなく、隠れられそうなところもない。脇道があるのかと少し前進してみたが、どうやらしばらくは一本道のようだった。
(……おかしい)
間違いなく黒猫がこの路地に入ったのを目にした。それなのに、見つからないことにロキは疑念を抱かずにはいられなかった。
追跡していた黒猫との距離を考えると、角を一つ曲がっただけで完全に見失うのは妙だ。
「上に逃げたんじゃないか?」
確かに身軽な猫ならあり得るかもしれない。
だが、トールの推測にロキは素直にうなずけなかった。
手近の建物を見上げる。
建造物の途切れた先に見えるのは、空の青と白く輝く太陽で、探す黒は映らない。
「ロキ」
トールが名前を呼ぶ。どこか気遣うような口調は、言外に黒猫の捜索を諦めることを提案している。
ロキは釈然としない気分で頭を下げて、短く嘆息した。
悔しいが、諦めるしかないのだろう。また運良く出会えるのを待つしかない。
(何か手がかりになったかもしれないのに……)
探すことを断念する選択肢を選びながらも、未練が足を引き留め、目を周囲に向けさせる。
「ロキっ!」
唐突にトールの余裕のない声が聞こえてきた。
何だとロキが聞き返すどころか、振り向く暇すらなかった。片腕をつかまれ、抵抗という判断を下す前に強い力で引っ張られた。
「いっ……!」
いきなりのことに足がついていかず、よろけたロキの体がトールにぶつかる。
ガシャンッ、と硬質な音が近くで響いた。
「危なかったな」
頭の上から、ほっとしたようなトールの声が降ってくる。
……何が、だ。
ロキがゆるゆると茶色の瞳の先を追って碧眼を向けると、石畳の上の乱雑に散らばったいくつもの破片に行き当たった。食器だろうか置物だろうか。ばらばらになっていて原型はもはやわからない。
しかし、ロキにとっては物の正体よりも視界のそれがついさっきまで自分がいた場所にあることのほうが気にかかった。
耳に届いた硬い音色は、あれが落下して砕けた音だったのだろう。トールが自分をあの場から離れさせてくれたおかげで、大事に至らなかった。
「………」
ロキは腕をつかんでいるトールの手を振り放した。落下物のそばまで進み、素早く周囲に視線を走らせた。
誰もいない。何の気配も感じない。あやまって物が落ちてきそうなところもない。
いや。
正面にある建物の二階の窓だけが開いている。黒猫を探して視線をやったときは開いていなかった。
ロキは建物と自分が立っていた場所との距離を考えて、そこからなら充分に可能性があると答えを導き出した。
躊躇うことなく建物の扉に駆け寄って取っ手をつかむ。扉はこめた力のとおりに難なく動いた。
「おい、ロキ?」
不思議そうなトールの呼びかけにロキは顔だけで振り返ると、
「そこで怪しいやつがいないか見張ってろ」
言い放つや、返事を聞かずに建物の中に足を踏み入れた。
「え、あっ、おい……」
閉まっていく扉の隙間からトールの戸惑う声がしたが、ロキは一切気にかけなかった。意識は今やすっかり前にある。
――腹立たしい。
ただでさえ街に着く前から気分が悪く、たどり着いた街の現状に気が沈む。そんなときに何者かに狙われたとあれば、無視なんてできるはずがなかった。
灯りのついてない建物の中は薄暗く、静まり返っている。広さはさほどなく、小綺麗な一般の住宅といった印象だ。
ロキは周囲に目と耳を立てて奥に足を進めた。すぐに部屋を二部屋見つけたが、どちらも扉を開けた先には何もなく、誰もいなかった。がらんとした空間ばかりが広がり、生活に必要な調度品さえないことに奇妙なものを覚える。
(誰も住んでないのか?)
物音は自分の足が木の床を踏む軋んだ音以外なく、生き物の気配も感じられない。
ロキは眉を寄せて、突き当たりを右に折れた。
上へ続く階段はそこにあった。階段よりもさらに延びる廊下の向こう側は台所、水場のようだ。しかし、例によって誰かどころか、調理器具などのちょっとした道具も見当たらない。
ロキは足を戻し、注意深く階段の果てを見据えた。外からの光が届きにくいため、奥へ行くほど闇が濃くなっている。最上段はうっすら見える程度だ。
「………」
腰にある短剣を確認するように手で一度触れてから、ロキは段に足をかけた。
ぎし、ぎし、と床よりも大きく足音が鳴る。
階段はふたり並ぶのがやっとの広さで足元も良くない。ここで襲われでもしたら厄介だ。
高まる緊張の中、一段一段慎重に階段を上がりきった先には、扉が一つあった。他に進める場所はない。
一階で見たのと同じ何の変哲もない扉だ。この扉が外から見た、開いていた窓のある部屋だろうか。もしそうなら何者かが潜んでいる可能性が高い。
ロキは一層警戒を強めて扉を開いた。
真っ先に開け放たれた窓が目につく。
(ここか)
だが、室内には誰もおらず、ここも何もなかった。ただ四角い空間が広がっているだけだ。
(……どういうことだ?)
部屋を見回したロキの表情に険しさが増す。
ここに着くまでの間に人影らしきものは一切見ていない。これ以上部屋や廊下はなかった。身を隠すことができそうな場所もなかった。なのに、自分を狙った犯人が見つからないなんて、おかしい。
(この建物にはもういないのか?)
碧眼が開けっ放しの窓をとらえる。
可能性は、ある。
犯人が外に逃げ出していないかを確認するためにロキは、一方的に待機を命じたトールに声をかけようと窓から顔を出した。
「っ、!?」
考えていた言葉は、発する前に頭の中で消滅した。
とっさにロキは自分が何かを間違えたのだと思った。しかし、建物の中での行動と路地との位置関係の記憶を何度思い返しても、非を感じる部分はなかった。ならば、自分以外にあるのかと考えたが、この状況下であのトールが無断で勝手な行動を取るとは思えなかった。
(どうなってるんだ?)
ロキが困惑しながら眼下を見つめる。
覗いた窓の外、路地に残してきたトールの姿がどこにもなかった。